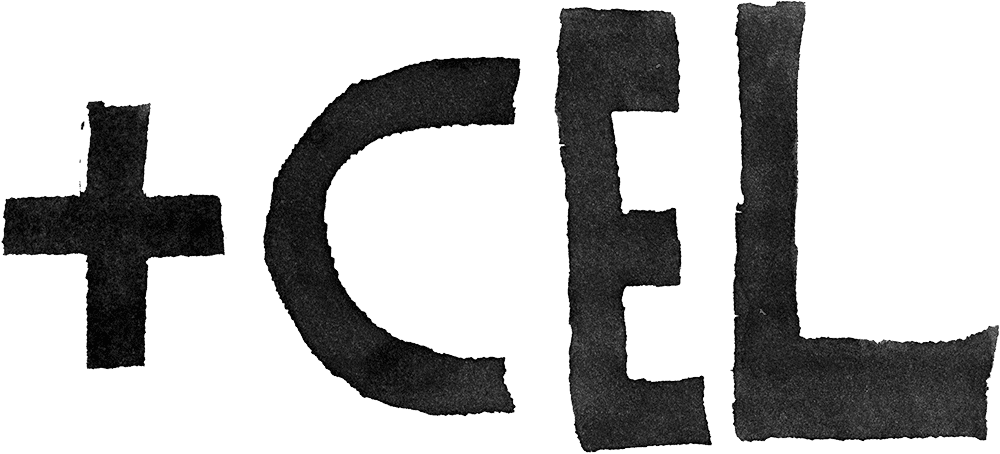新しいランドセルが愛すべき存在になるために。
柴田文江さんインタビュー<前編>
新しいランドセルが愛すべき存在になるために。
柴田文江さんインタビュー<前編>
〈+CEL〉では2026年より、プロダクトデザイナーの柴田文江さんが手がけた〈ARTISAN〉と〈NOBLE〉というふたつのモデルが登場しました。ランドセルとして違和感がないのに、まったく新しい機能と可愛さを備えたモデルは、どのように生まれたのか。柴田さんにデザインの裏側を聞きました。
photo: Norio Kideratext: Toshiya Muraokaedit: Naoko Yoshida
――デザインを依頼されて、まず、どんなことを考えましたか?
柴田文江(以下、柴田) 入学式でランドセルを背負った我が子を見て、その成長に感動したり、あるいはお子さん自身が小学生になるトキメキを感じたり、ランドセルにはご家族の思いが込められていますよね。見た目やスタイルを完全に変えてしまうと、ランドセルが持っている情緒のようなものが崩れてしまう。ですから、みんながイメージする「ランドセルらしさ」を残しつつ、新しさを出していく必要があるだろうと。その中でスタンダードなものと革新的なものと、ふたつのコンセプトで考えました。
――スタンダードなモデルが、〈ARTISAN〉ですね。
柴田 職人という意味の名の通り、技術の粋を集めたモデルです。今までのランドセルには、私には不思議なところがいっぱいあって、そのひとつが背当ての白いこと。元々、牛革で作られていた名残のようですが、自分が子どもだった時に、その白い背当てが薄汚れていったことを覚えているんですね。昔は素材が限られていたこともあるんでしょうけれど、なぜ今も白いのかと。アイコンのひとつだとは思いますが、どこかおもちゃのような印象を抱いてしまう。ランドセルも、きちんとカバンとして考えて、もう少しソリッド感のあるように作りたかったので、背当ても、肩ベルトの裏も同色にしました。

水筒がぴったりと入る、〈ARTISAN〉モデルのボトル入れ。革を編んだような細工にすることで、「よりカバンとしての佇まいを引き立てると思います」と、柴田さん。調整、取り外し可能で、機能性も追求されています。
――ランドセルは、カバン。当たり前のことですが、改めて捉え直すことで新しさが生まれていくんですね。
柴田 大学で地域の方々に参加していただく授業をすると、子どもたちがみんな席に着くなりカバンから水筒を出して机に置くんですね。一体、ランドセルのどこに入れているんだろう? と思っていました。なので、ボトル入れをARTISAN的に革の細工で作りました。よりカバンとしての見え方を助長してくれています。オリジナルの金具を作ったり、革の切り口を処理したり、細部にデザインを織り込んでいますが、すべてを図面に起こすことはできないので、職人さんたちの知見も多く入っている。私というデザイナーと、〈+CEL〉の職人さんでなければ作れないランドセルになったと思います。

――ご自身の記憶も、デザインを考える上では重要なのですか?
柴田 そう言えば、と「疑問」を思い出す感覚でしょうか。私が使っていたランドセルは雨に濡れても水を弾いて、便利だけど自分のものになり切らない妙な気持ちを抱いていたことを覚えています。愛着はまったく持っていなかった。当時の親たちも、我が子が小学生になるというワクワク感はあっても、モノとしてランドセルを買う魅力は感じていなかったんじゃないかな。

PROFILE

柴田文江(しばた・ふみえ)
デザインスタジオエス代表。山梨県出身。甲州織物を営む家庭に育つ。エレクトロニクス商品から家具、医療機器、ホテルのトータルディレクションなど、さまざまなデザインを手がける。エル・デコインターナショナルデザインアワード照明部門グランプリ受賞、Red Dot Award Best of the Best、iF Design Award金賞など受賞歴多数。多摩美術大学教授。著書『あるカタチの内側にある、もうひとつのカタチ』。